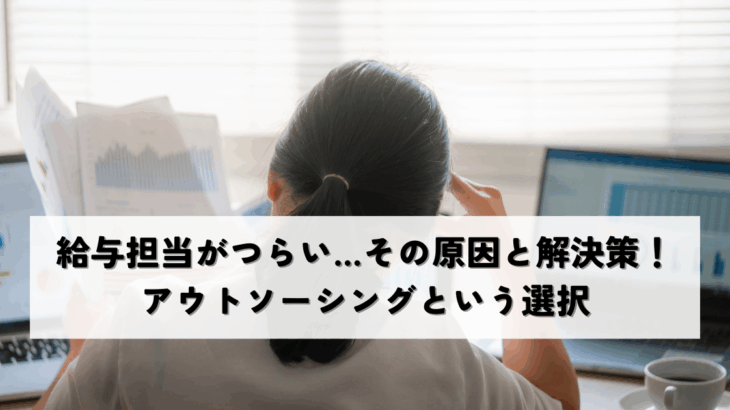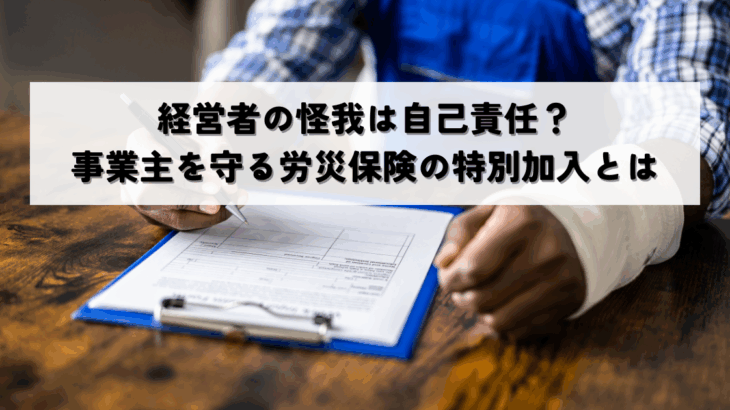従業員の遅刻や早退は、多くの企業で発生しうる勤怠上の問題です。
これらの状況が発生した際、給与からどのように控除すべきか、その計算方法や注意点について、疑問をお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。
今回は、従業員の遅刻・早退時の給与控除について、基本的な考え方から具体的な運用方法までを解説します。
控除の計算方法
ノーワークノーペイ原則
従業員の遅刻・早退時の給与控除は、「ノーワーク・ノーペイ」の原則に基づきます。
これは、働いていない分の賃金は支払う義務がないという労働契約における基本的な考え方です。
会社は従業員が提供した労働に対して賃金を支払う義務がありますが、従業員側の都合で労働が提供されなかった時間については、その分の賃金を支払う必要はありません。
この原則は、正社員だけでなく、パートやアルバイトなど、あらゆる雇用形態の従業員に適用されます。
ただし、会社側の都合や問題によって生じた欠勤、早退、遅刻については、この原則による控除はできません。
あくまで、従業員自身の都合による場合に適用されるものです。
具体的な計算手順
遅刻・早退控除の具体的な計算方法は法律で細かく定められていませんが、一般的には、月給額をその月の所定労働時間(または就業規則で定めた月平均所定労働時間)で割り、1時間あたりの賃金を算出します。
そして、その1時間あたりの賃金に、遅刻・早退した時間数を掛けて控除額を計算します。
計算式は「月給与額÷(月)所定労働時間数×早退・遅刻時間数」となります。
例えば、月給20万円で、1か月の所定労働時間が168時間(1日8時間×21日勤務と仮定)の従業員が、合計5時間遅刻・早退した場合、控除額は「200,000円÷168時間×5時間」で約5,952円となります。
この計算の基となる月給与額に、各種手当を含めるかどうかは、会社の規定によります。
一般的には、住宅手当や家族手当のような福利厚生的な手当は、従業員の生活を支える性質を持つため、控除の対象から除外することが望ましいとされています。
1分単位計算の扱い
遅刻・早退の控除額は、必ず1分単位で正確に計算する必要があります。
例えば、3分の遅刻に対して15分単位で切り上げて計算することは、労働基準法や民法に違反する可能性があります。
これは、実際に労働しなかった時間を超えて賃金を控除することになり、従業員にとって不利益となるためです。
同様に、計算結果に生じた1円未満の端数も、従業員に不利益とならないよう切り捨てるのが原則です。
正確な勤怠記録と1分単位での計算が、法的なトラブルを防ぐ上で不可欠となります。

従業員遅刻早退の注意点
就業規則への明記
早退・遅刻控除の計算方法には法律による明確な定めがないため、その取り扱いを就業規則に具体的に明記することが最も重要です。
明記すべき事項としては、遅刻・早退の定義、申告方法、突発的な場合の対応、そして最も重要な控除の計算方法や、どの手当を控除対象に含めるかといった点です。
就業規則に記載がない、または不明確な場合、「勝手に給与が減らされた」といった従業員とのトラブルにつながる可能性があります。
給与形態別の扱い
遅刻・早退控除の適用可否や計算方法は、従業員の給与形態によって異なります。
「完全月給制」の場合、遅刻・早退があっても原則として減額されませんが、多くの会社で採用されている「日給月給制」や「月給日給制」では、遅刻・早退した分の基本給などを控除することが可能です。
「年俸制」の場合は、就業規則に控除方法が明記されていれば、年俸額を年間所定労働時間で割って計算した額を控除できます。
「歩合給制」では、基本給部分のみを控除対象とし、歩合部分は控除しません。
「フレックスタイム制」では、総労働時間を満たしていれば、コアタイムの遅刻・早退であっても原則として控除は発生しません。
ただし、総労働時間が不足した場合は、その分を控除することが可能です。
従業員への周知方法
就業規則に遅刻・早退控除に関する規定を定めたら、それを従業員全体にしっかりと周知することが不可欠です。
就業規則の変更点や、給与計算への影響などを、説明会や社内報、イントラネットなどを活用して、分かりやすく伝える必要があります。
従業員がルールの内容を理解し、納得した上で運用することが、信頼関係の構築とトラブル防止につながります。

まとめ
従業員の遅刻・早退時の給与控除は、ノーワーク・ノーペイの原則に基づき、正確な計算と適切な運用が求められます。
就業規則への明記、1分単位での正確な計算、そして給与形態ごとの扱いを理解することが重要です。
これらの点を踏まえ、従業員への丁寧な周知を行うことで、労務トラブルを防ぎ、公正な給与計算を実現できるでしょう。