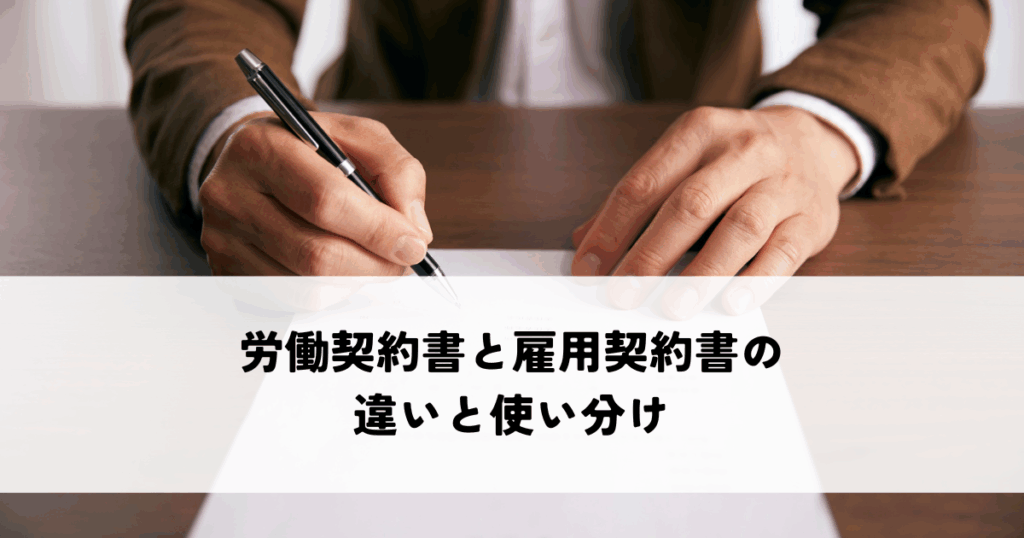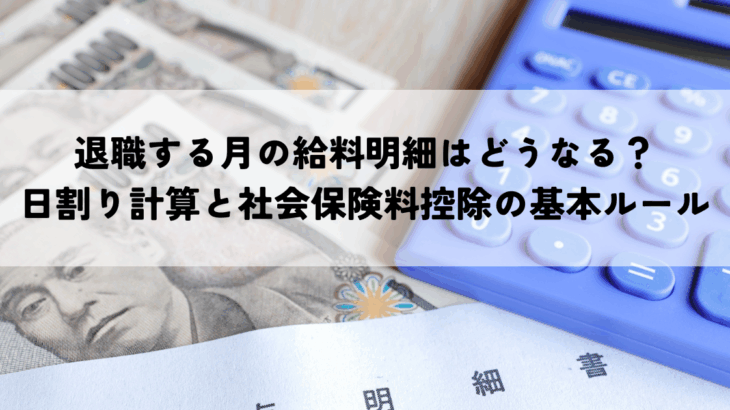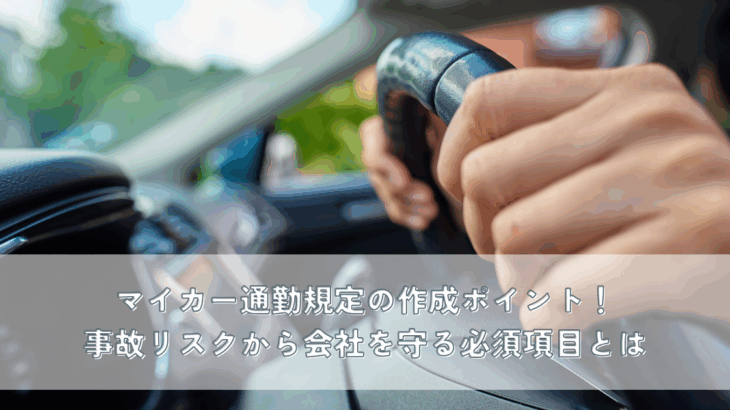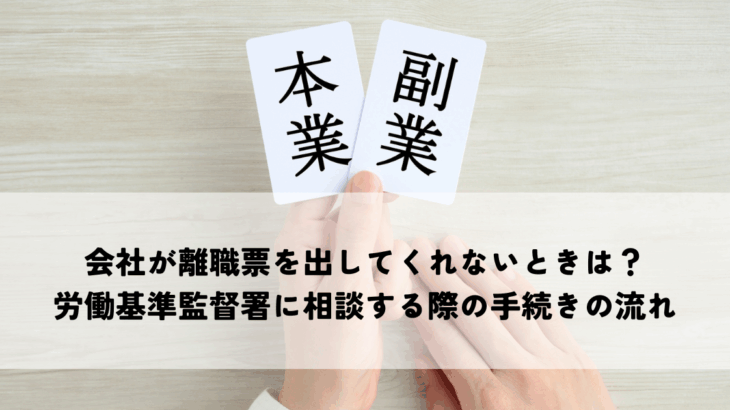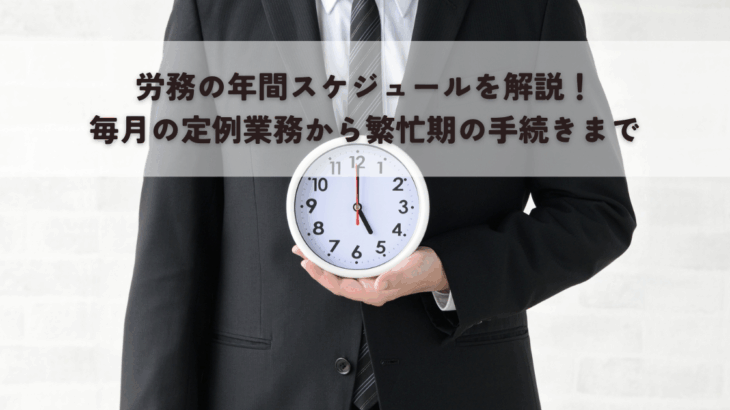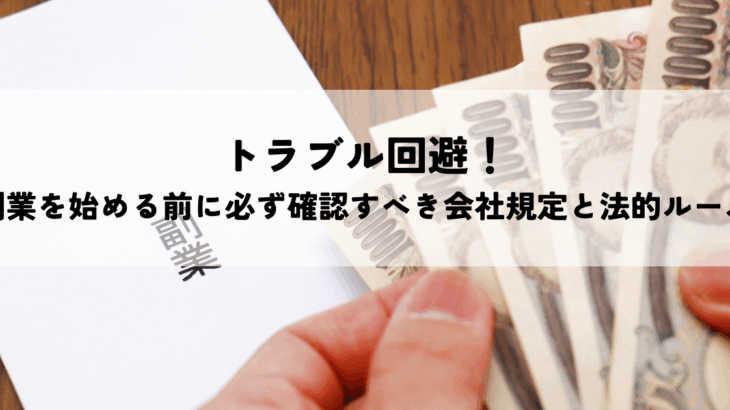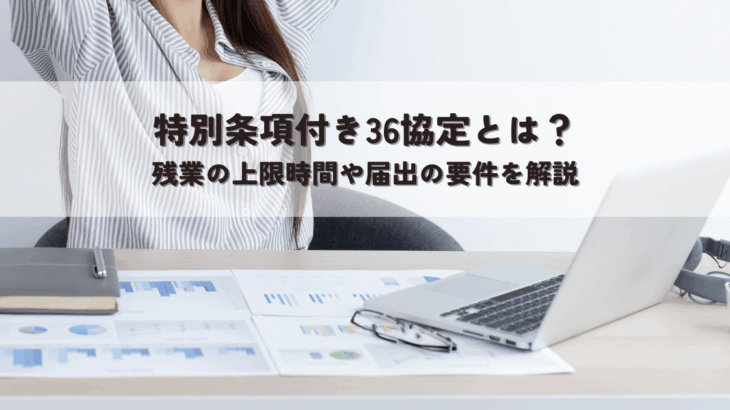従業員を雇用する際、「労働契約書」や「雇用契約書」といった書類を目にします。
これらは似ているようで、違いが分かりにくいと感じる方も多いのではないでしょうか。
実は、法的な観点や実務の上では、この2つの書類の名称に大きな違いはありません。しかし、雇用契約を結ぶ上で、企業が必ず対応しなければならない、もっと重要な書類が存在します。
今回は、労働契約書と雇用契約書の実際の扱われ方と、企業に作成・交付が義務付けられている「労働条件通知書」との違いについて、分かりやすく解説します。
「労働契約書」と「雇用契約書」に違いはない?
実務上は同じものとして扱われる
結論から言うと、「労働契約書」と「雇用契約書」は、名称が違うだけで法的には同じものと考えて問題ありません。
法律(労働契約法)では、労働者と使用者の間で結ぶ契約を「労働契約」と呼び、民法では「雇用契約」という用語が使われますが、指している内容は基本的に同じです。
どちらの名称の書類を使ったとしても、その法的な効力は変わりません。重要なのは、書類の名称ではなく、その「中身」です。
契約で重要なのは「名称」より「内容」
雇用に関するトラブルを防ぐために最も重要なのは、労働時間、賃金、業務内容といった「労働条件」について、企業と労働者の双方が明確に合意していることです。
その合意を証明するために作成されるのが、「労働契約書」や「雇用契約書」と呼ばれる書面です。
つまり、これらの書類は、口頭でも成立する「労働契約(雇用契約)」の内容を可視化し、後のトラブルを避けるための「合意の証拠」として非常に重要な役割を果たします。
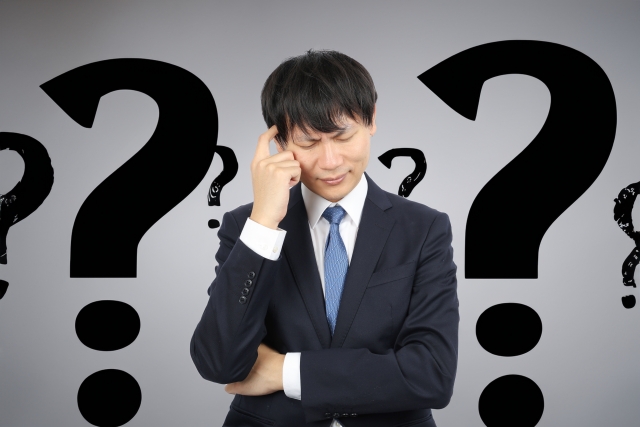
本当に重要なのは「労働条件通知書」
法律で交付が義務付けられた書類
企業が従業員を雇用する際、名称がどちらでもよい「契約書」以上に重要なのが「労働条件通知書」です。
労働基準法第15条により、企業は労働者に対して、賃金や労働時間などの特定の労働条件を明示した書面を交付することが法律で義務付けられています。
この「労働条件通知書」を交付しない場合、労働基準法違反となり、罰則の対象となる可能性があります。
雇用契約書と労働条件通知書の違い
2つの書類の最も大きな違いは、以下の点です。
・労働条件通知書:
企業が労働者へ一方的に通知する書類。法律で交付が義務付けられている。
・雇用契約書:
企業と労働者が労働条件に双方が合意したことを証明する書類。
法律上の作成義務はない(ただし、トラブル防止のため作成が強く推奨される)。
このように、両者は役割が異なります。
通知義務を果たし、かつ合意の証拠を残すために、実務上は両方の性質を兼ね備えた書類を作成するのが一般的です。

実務では「労働条件通知書 兼 雇用契約書」がおすすめ
一通で二つの役割を果たす
最も確実で効率的な方法は、「労働条件通知書 兼 雇用契約書」というタイトルの書類を作成することです。
この形式であれば、労働条件通知書として法律で明示が義務付けられた項目を網羅しつつ、末尾に署名・捺印欄を設けることで、労働者がその内容に合意したことの証明(雇用契約書の役割)も同時に得られます。
書類を1通にまとめることで、交付漏れを防ぎ、管理も簡素化できるため、多くの企業でこの形式が採用されています。
記載すべき主な項目
「労働条件通知書」として、最低限以下の項目は明記する必要があります。
・労働契約の期間
・就業の場所・従事する業務の内容
・始業・終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、交替制勤務をさせる場合は就業時転換(交替期日あるいは交替順序等)に関する事項
・賃金の決定・計算・支払方法、賃金の締切り・支払の時期に関する事項
・退職に関する事項(解雇の事由を含む)
これらの必須項目に加え、企業のルールなどを盛り込み、労使双方にとって分かりやすい書類を作成することが大切です。
まとめ
「労働契約書」と「雇用契約書」は、実務上ほぼ同じものを指す書類であり、名称に法的な優劣はありません。
それ以上に企業が注意すべきは、法律で交付が義務付けられている「労働条件通知書」です。
企業の法務リスクを減らし、従業員との信頼関係を築くためには、労働条件通知書の必須項目を満たし、かつ契約内容への合意を証明できる「労働条件通知書 兼 雇用契約書」を作成・締結することが最も確実な方法と言えるでしょう。
雇用に関する書類の作成や、自社の運用に不安がある場合は、専門家である社会保険労務士に相談することをおすすめします。
長野県諏訪地域の企業様は、ぜひ一度、諏訪労務管理センターへご相談ください。