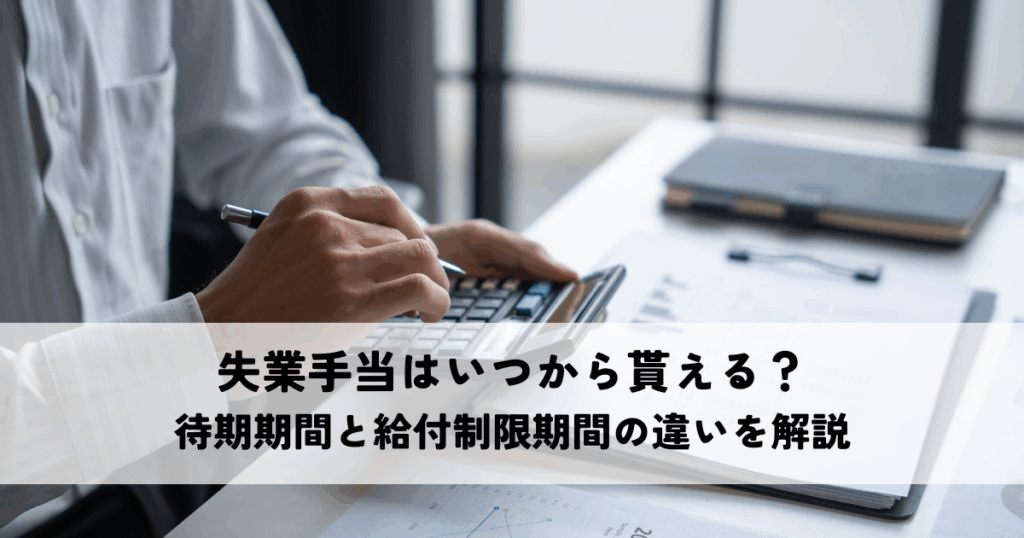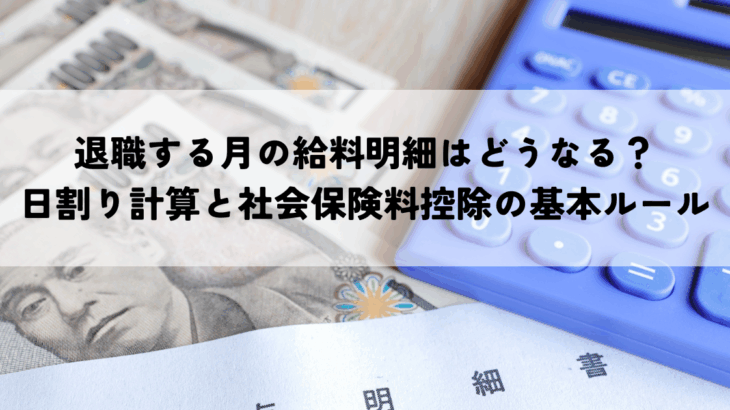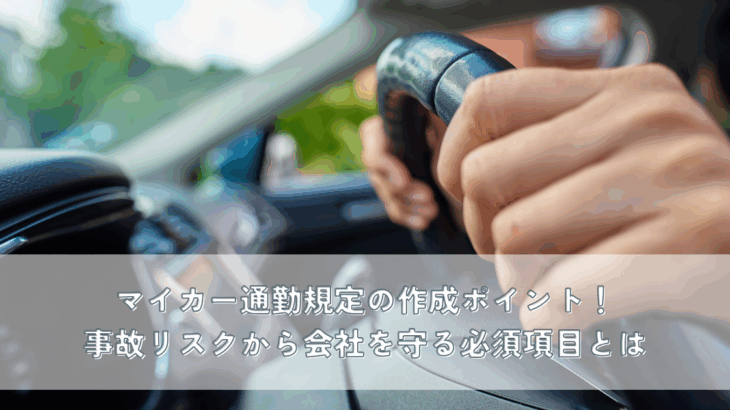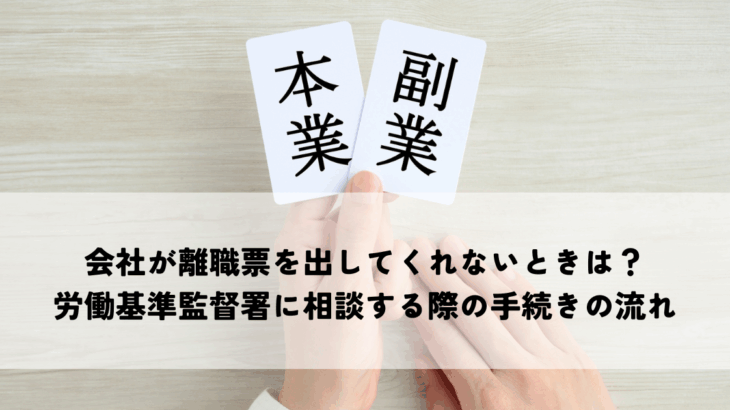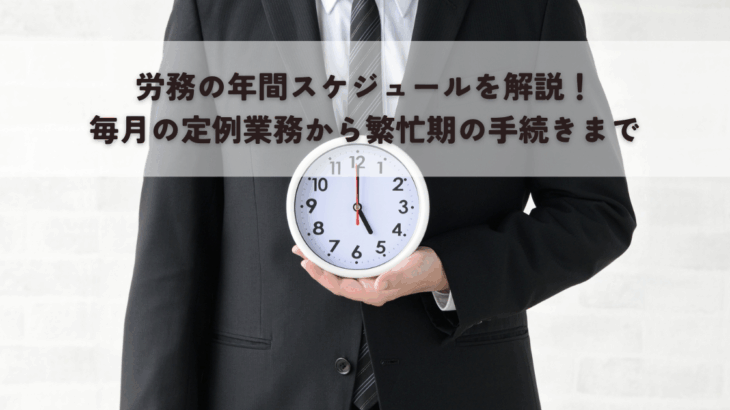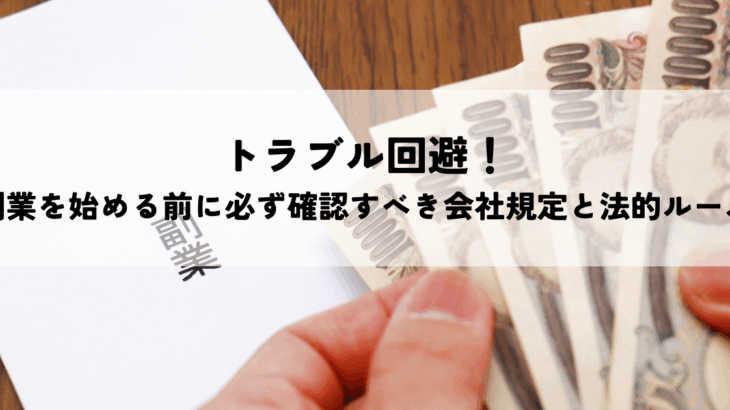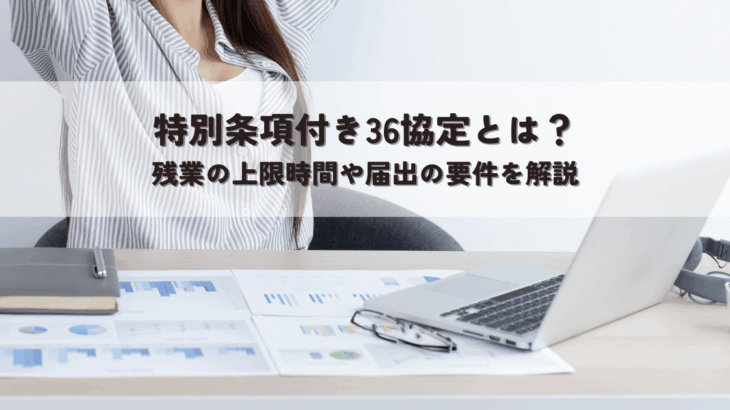退職や失業の際に、生活の支えとなる雇用保険の基本手当(失業手当)。しかし、「手続きをしてもすぐには貰えない」ということをご存知でしょうか。
雇用保険には「待期期間」や「給付制限期間」といった制度があり、これらを正しく理解していないと、資金計画に大きな影響が出てしまう可能性があります。
今回は、雇用保険の基本手当がいつから支給されるのか、待期期間と給付制限期間の違い、そして受給するための要件について分かりやすく解説します。
基本手当(失業手当)を受給するための要件
まず、雇用保険の基本手当は、誰もが必ず受け取れるわけではありません。
受給するためには、以下の要件を満たす必要があります。
①ハローワークで求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があるが、就職できない「失業の状態」にあること。
②離職日以前2年間に、被保険者期間(雇用保険に加入していた期間)が通算して12か月以上あること。
ただし、会社の倒産・解雇など、やむを得ない理由で離職した場合(特定受給資格者または特定理由離職者)は、離職日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上あれば、要件を満たします。

支給開始までの流れ|「待期期間」と「給付制限期間」
ハローワークで手続きをしてから、実際に手当が振り込まれるまでには、一定の期間がかかります。
ここが最も重要なポイントです。
全員に適用される「待期期間(7日間)」
離職理由にかかわらず、ハローワークで求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から通算して7日間は、基本手当が支給されません。これを「待期期間」と呼びます。
この期間は、本当に失業状態にあるかを確認するためのもので、この7日間が経過しないと、その後の支給は始まりません。
退職理由によって発生する「給付制限期間」
待期期間の7日間が終わった後、退職した理由によって、さらに手当が支給されない期間が設けられる場合があります。
これを「給付制限期間」と言います。
・給付制限がないケース
会社の倒産、解雇、契約期間の満了など、会社都合や正当な理由で離職した場合は、給付制限はありません。7日間の待期期間が終われば、失業認定を経て支給が開始されます。
・給付制限があるケース
転職や独立など、自己都合で退職した場合や、自己の責めに帰すべき重大な理由(重責解雇)で離職した場合は、原則として1か月間(場合によっては3か月間)の給付制限が課せられます。
つまり、自己都合で退職した方は、「待期7日間+給付制限2か月」が経過しないと、手当を受け取ることができないのです。

受給中に求められることと支給期間
失業の認定と求職活動実績
基本手当は、原則として4週間に1度、ハローワークへ行き「失業認定申告書」を提出し、「失業の認定」を受けることで支給されます。
認定を受けるためには、前回の認定日から次の認定日までの間に、原則として2回以上(給付制限期間中は3回以上の場合あり)の求職活動実績が必要です。求職活動が確認できない場合、その期間の手当は支給されないため注意が必要です。
手当を受けられる日数(所定給付日数)
基本手当が支給される上限日数を「所定給付日数」と呼びます。
この日数は、年齢、雇用保険の被保険者であった期間、離職した理由などによって異なり、90日から360日の間で決められます。
まとめ
雇用保険の基本手当は、退職後すぐに受け取れるわけではありません。
まず、離職理由にかかわらず7日間の「待期期間」があります。さらに、自己都合で退職した場合は、その後原則1か月の「給付制限期間」が設けられます。
この仕組みを知らないと、退職後の生活設計に大きな影響を及ぼす可能性があります。ご自身の退職理由がどちらに該当するのか、いつから支給が始まるのかを正しく把握しておくことが大切です。
雇用保険の手続きやご自身の受給資格について不明な点がある場合は、お近くのハローワークや、専門家である社会保険労務士にご相談ください。
諏訪市を中心に雇用保険に関するお悩みがありましたら、お気軽に諏訪労務管理センターまでご相談ください。